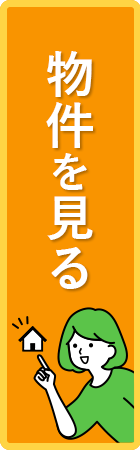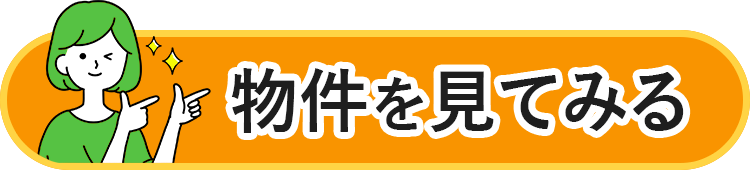中小建売業者が直面する過酷な現実
私は長年にわたり、エンドユーザー向けの不動産営業に従事してきました。
チームメイトのフォローも含め、年間100件以上、いやそれ以上かもしれません。マイホームの契約に関わった時期もありました。現在はtoB向けの営業を行っており、以前のようにエンドユーザーのお客様と直接お会いする機会はなくなりました。
「戸建てはやめとけ」――驚きの声の理由
あるタイミングから、エンドのお客様を担当することがほとんどなくなったのですが、今振り返れば、ギリギリのところで大きなトラブルに巻き込まれずに済んだのかもしれません。
そんな中、建売住宅の原価の実情を知るため、複数の建売業者の方とお話しする機会がありました。
私からは何も切り出してないのに、「あんたとこで、戸建てをやるつもりならやめときや((標準語:あなたの会社で、戸建て住宅販売に参入するつもりなら、やめておいた方がいいよ))」と言われ驚きました。
理由を聞くと、こう返ってきました。「全く利益が出ない」のだそうです。
住宅業者を苦しめる「クレーム」というリスク
土地の価格や工事費の高騰はもちろんですが、一番の不安要素はーー
「顧客のクレーム」だそうです。
安くない土地を仕入れ、スペックの高い住宅を建てて住宅の品質を維持しながら工事費を抑えながら商品化する。そして契約が決まっても、残るのはわずか200万円程度の粗利…。
恐いのはこの後です。
以前から「住宅産業はクレーム産業」と言われており、ご購入いただいた住宅に、お客様が実際に住んでから、不具合が見つかることが多いのです。
正当な不具合対応と「あり得ないクレーム」
例えば、「ドアの建て付けが悪い」「排水の流れが悪い」「床と壁の間に大きな隙間がある」など。
もちろん不具合に対して、建売業者は誠意をもって対応します。これは当然のことです。
しかし、もっと厄介で恐いのが「あり得ないクレーム」です。
消費者保護の名のもとに、クレームはすべて受け入れて当然で、全て解消すべきと考える方もいらっしゃいます。
正当な指摘であれば、対応は当然ですが、いわゆるモンスタークレーマーが相手になると話は別です。クレーム対応に人手も時間も取られ、気づけば赤字に転落することも珍しくありません。
詳細は控えますが、なかには「この家、買い取れ」と迫るケースもあるそうです。実際に買取りすることはまずありませんが、お客様との関係は完全に悪化し、良い結果にはつながりません。
住宅産業を蝕む「カスハラ」の影
こうしたモンスタークレーマーは年々増加しているといいます。
最近、カスタマーハラスメントを略した「カスハラ」という言葉をよく耳にするのも、無関係ではないでしょう。
苦労してつくった商品が赤字になるのなら、「もうこの事業、やめたい…」と思うのも、無理はありません。