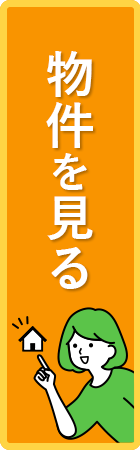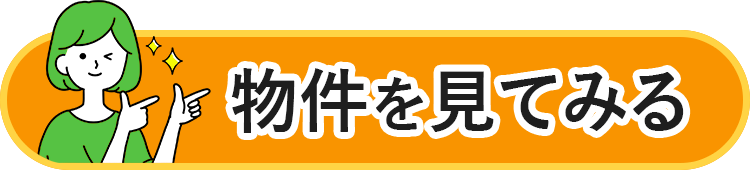モデルルームとして使用された物件が、完成後に「未入居物件」として販売されるケースがあります。
これらは一般の新築分譲住宅とは異なる「完成在庫」としての性質を持ち、時には相場よりもお得に購入できるチャンスにもなります。
しかし、魅力的な価格や設備が整っている反面、「中古物件扱いになる」「住宅ローン控除などが適用されない場合がある」といった見落とされがちな注意点も存在します。
本記事では、モデルルーム使用後物件の特徴、購入のメリットと注意点、さらに賢い買い方まで詳しく解説します。
モデルルーム使用後物件とは?

モデルルームの基本概念
モデルルームとは、分譲マンションや戸建て住宅の販売時に、実際の住戸を使って生活イメージを見せるための「展示住戸」です。一般に公開され、多くの人が内覧する目的で使用されます。
住宅展示場とは異なり、実際に販売される住戸を使用するため、見学する購入検討者にとって非常にリアルな住まいのイメージを提供する重要な役割を果たしています。
モデルルームでは、家具やカーテン、照明器具などのインテリアが設置され、実際の暮らしをイメージしやすいよう工夫が施されています。週末には多くの見学者が訪れるため、一般的には半年から1年程度の期間にわたって展示されることが多いです。
販売されるまでの流れ
展示期間が終了すると、モデルルームとして使用されていた住戸が一般向けに販売されます。この物件が「モデルルーム使用後物件」と呼ばれるものです。
販売時期は、通常のマンション販売が一段落した段階や、建築会社・デベロッパーの決算期に合わせて行われることが多く見受けられます。
重要ポイント:一見すると新築のように思えますが、法律的には「人が使用した形跡がある」「建築から1年以上経過している」などの理由で、中古扱いになることがあります。
国土交通省の住宅瑕疵担保履行法によると、「モデルルームが工事完了後1年以内に販売された場合、資力確保措置の対象になります」とされており、この分類によって、購入時の税制優遇や保証の内容が大きく異なるため、確認が必要です。
モデルルーム物件の具体的なメリット
1. 相場より価格が抑えられている
モデルルーム物件は通常の新築マンション・住戸と比較して、数十万円から数百万円安く販売されるケースが多く、販売時には「値下げ」や「価格交渉」に応じてもらえる可能性も高くなります。
展示用として使用された経緯から、住戸には使用感がある可能性があり、それが価格に反映されることが多いため、条件次第では非常にお得な買い物となります。特に、建築会社やデベロッパーの決算期などは、在庫整理の意味合いも含めて、さらなる価格交渉の余地が生まれることもあります。
価格差の目安:実際の市場では、同じ建物内の他の住戸と比較して5~15%程度の価格差が生じることが一般的で、立地や設備によっては数百万円の差額になることも珍しくありません。
2. 生活設備やオプションが充実
モデルルーム物件には、販売促進のために設置された家具、カーテン、照明、エアコンなどの生活設備がそのまま付いてくるケースがあります。これらの設備は、購入者の生活スタイルや部屋に合わせて選ばれた高品質なものが多く、個別に購入すると100万円以上の費用がかかることも珍しくありません。
購入後に一から揃える必要がないため、初期費用を大きく抑えることができ、実質的な「住み始めコスト」が非常に安価になります。
特に、新婚世帯や単身赴任世帯など、すぐに生活を始めたい方にとっては大きなメリットとなります。
また、インテリアコーディネーターがデザインした空間をそのまま手に入れることができるため、自分でインテリアを選ぶ手間や時間を大幅に削減できる点も見逃せません。
3. 実物確認済みで安心感がある
通常の新築物件では、図面やパースだけで購入を判断する必要がありますが、モデルルーム物件は実際に内覧した住戸をそのまま購入できるため、日当たりや動線、眺望などを見学時に事前に把握できる安心感があります。
間取りの使い勝手や収納の容量、コンセントの位置なども事前に確認できるため、入居後に「思っていたのと違った」というトラブルを避けることができます。
特に、家族構成や生活スタイルに合った住まいかどうかを実際に体感して判断できる点は、大きな安心材料となります。
4. 即入居が可能
完成済みの物件であるため、購入後の入居までの時間が短く、急いで住み替えたい人や、生活プランに合わせてすぐに新生活を始めたい人にとっては理想的な選択肢です。
通常の新築物件の場合、契約から引き渡しまで数ヶ月から1年程度の期間を要することが多いですが、モデルルーム物件であれば、契約から1~2ヶ月程度で引き渡しを受けることが可能です。転勤や結婚、出産など、住み替えのタイミングが決まっている場合には、このスピード感は非常に重要な要素となります。
購入時に注意すべきポイント

1. 法的には「中古物件扱い」となる場合がある
モデルルーム使用後の物件は、新築と異なり「一度でも人が使った」「1年以上経過した」などの理由から「中古物件」として扱われる場合があります。
2022年度税制改正の影響:制度が大きく変更された住宅ローン減税では、中古住宅の築年数要件が緩和され、新耐震基準など一定の条件を満たしていれば従来よりも利用しやすくなりました。
しかし、中古マンションでも、住宅ローンを利用して家を購入した場合、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」により、購入後10年間、年末のローン残高の0.7%が所得税や住民税から控除されますが、新築物件とは条件が異なる場合があります。
この場合、住宅ローン減税や登記費用の軽減措置、固定資産税の軽減措置などの新築向け優遇制度の対象外となる可能性があるため、事前に不動産会社や税理士に相談が必要です。中古物件の場合、築25年以内が目安です。
ただし、新耐震基準を満たしている証明書がある場合は、25年を超えていても対象になりますという条件もあるため、購入前の確認・チェックが重要です。
2. 瑕疵担保責任や保証期間に注意
未入居とはいえ、人の出入りがあった物件であるため、床や壁に細かなキズがあることも。特に水回りやエアコンなどの設備機器の保証期間が、展示開始時からカウントされている可能性があるため、注意が必要です。
保証期間について:売主が個人であり宅地建物取引業者による媒介の場合は、数ヶ月と長くありません。一般的には3カ月と言われています。
モデルルーム物件の場合、売主は通常デベロッパーや建築会社であるため、個人売主よりも手厚い保証が期待できますが、設備の保証期間については個別に確認が必要です。
契約時には、保証書の有無や保証内容、住宅の瑕疵保険とは、住宅の不具合・欠陥に対する保険で、不動産会社や保証会社が提供する「保証」とは異なりますため、既存住宅瑕疵保険の加入可能性なども確認しましょう。
3. 設備や家具の処分が必要な場合も
オプション設備が一式残っているのはメリットでもありますが、不要な家具がある場合、撤去費用を買主が負担することもあります。
特に、モデルルーム用に設置された家具は、一般的な住宅用途には向かない装飾的なものが含まれている場合があります。
契約時に家具の所有権がどちらにあるのか、不要な家具の処分費用は誰が負担するのかを明確にしておくと安心です。また、家具の搬出によって床や壁に損傷が生じる可能性もあるため、事前の状態確認も重要です。
4. 数が少なく、早い者勝ちの傾向がある
モデルルーム物件は、通常1物件に1住戸しか存在しないため、販売タイミングを逃すと二度と同じ条件での購入はできません。人気エリアや好立地の住戸は、即日成約することもあります。
そのため、購入を検討する場合は、事前に住宅ローンの事前審査を受けておく、購入予算を明確にしておくなど、迅速な意思決定ができる準備をしておくことが重要です。
どんな人におすすめ?購入者のタイプ別分析
即入居を希望する人
転勤や結婚、出産など、住み替えのタイミングが決まっている人にとって、モデルルーム物件の即入居可能という特徴は大きなメリットです。賃貸住宅の更新時期や、現住居の売却タイミングとの調整がしやすいのも特徴です。
コストパフォーマンスを重視する人
新築同等の住環境を、より安価に手に入れたい人には理想的な選択肢です。特に、初回購入者や若年世帯など、予算に制約がある場合には、価格面でのメリットが大きな決め手となります。
インテリアにこだわりがない人、または時間がない人
家具選びや部屋のインテリアコーディネートに時間をかけたくない人、またはその分野に自信がない人にとって、プロがデザインした空間をそのまま手に入れられるのは大きなメリットです。共働き世帯など、住まい選び以外に時間を割きたい人にも適しています。
実物重視の慎重な購入者
図面だけでは判断が難しい、実際の住環境を重視する人には、事前に内覧できるモデルルーム物件は安心感を提供します。
初回購入者にとっては、住まいの実際の使い勝手を確認してから購入できる点は重要な要素です。
購入時のチェックポイントと交渉のコツ

現地確認は必須
必ず現地にて床、壁、天井、サッシ、キッチンやバスルーム等水回り設備の状態を確認しましょう。特にキズ・汚れ・設備不良の有無を重点的に見てください。展示期間中に多くの見学者が出入りしているため、玄関周りや廊下、水回りなどは使用感が残っている可能性があります。
また、展示用の家具によって隠れていた部分の確認も重要です。家具の移動跡や、コンセント周りの状態なども含めて、総合的な住戸の状態を把握しましょう。
保証と税制の取り扱いを確認
住宅ローン控除の有無や、登記費用・固定資産税の軽減制度の対象になるか、事前に確認しましょう。
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・増改築する場合に、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除することができる制度ですが、中古扱いとなる場合は条件が異なります。
また、瑕疵保険に入れるかどうかも大切な判断基準です。購入前に、税理士や住宅ローンアドバイザーなどの専門家に相談することをお勧めします。
家具の所有権と処分の条件を契約前に確認
「家具付き」といっても、所有権がデベロッパーにある場合や、別売りオプションの場合もあるため、明細を確認しましょう。残置される家具のリスト作成、不要家具の処分方法、処分費用の負担者などを契約書に明記することが重要です。
また、家具の品質や耐久性についても確認が必要です。展示用の家具は見た目重視で作られていることもあり、実際の生活に適さない場合もあります。
価格交渉のタイミングを見極める
決算期や販売終了時期など、デベロッパーが在庫を減らしたいタイミングは、価格交渉のチャンスとなります。複数社で比較検討し、提示価格に根拠があるかを確認しましょう。
一般的に、3月の年度末、9月の中間決算期、12月の年末などは交渉がしやすいタイミングとされています。また、長期間売れ残っている物件の場合、デベロッパー側も価格交渉に応じやすい傾向があります。
モデルルームと注文住宅・モデルハウスとの違い
注文住宅との相違点
注文住宅は、建築会社と施主が相談しながら間取りや仕様を決めて建築する住宅です。一方、モデルルーム使用後物件は、あらかじめ決められた間取りと仕様で建築され、展示された住宅です。
注文住宅では、家族構成や生活スタイルに合わせた間取りの設計が可能で、内装や設備についても自由度が高いのが特徴です。しかし、設計から完成まで1年以上の期間を要し、費用も割高になる傾向があります。
モデルハウスとの違い
住宅展示場にあるモデルハウスは、純粋に展示目的で建築された建物で、一般的には販売されません。また、実際に販売される住宅よりも高仕様で建築されることが多く、現実的な住宅とは異なる場合があります。
一方、モデルルーム使用後物件は、実際に販売される住戸と同じ仕様で建築されているため、より現実的な住環境を把握できます。
住宅選びにおける事例とデザインの考慮
成功事例の紹介
実際にモデルルーム使用後物件を購入した家族の事例を見ると、多くの場合で満足度が高いことがわかります。
例えば、30代の共働き夫婦が購入したケースでは、家具や設備が一式揃っていたため、引っ越し後すぐに快適な暮らしを始めることができました。
また、単身赴任で急いで住まいを探していた40代男性のケースでは、価格の安さと即入居可能な点が決め手となり、予算内で理想的な住環境を手に入れることができたという事例もあります。
デザインと機能性のバランス
モデルルーム物件では、プロのインテリアコーディネーターがデザインした空間を手に入れることができますが、展示用のデザインが実際の生活に適しているかどうかの判断が重要です。
見た目の美しさだけでなく、収納の使い勝手、動線の効率性、メンテナンスの容易さなども含めて総合的に評価する必要があります。
住宅会社・デベロッパーとの相談方法
情報収集の重要性
モデルルーム使用後物件の購入を検討する際は、住宅会社やデベロッパーとの綿密な相談が不可欠です。物件の履歴、展示期間、見学者数、設備の保証状況など、詳細な情報を収集しましょう。
また、同じ建物内の他の住戸の販売状況や価格なども参考情報として有用です。市場価格との比較検討材料として活用できます。
契約条件の交渉
価格交渉だけでなく、引き渡し時期、家具の処分、アフターサービスの内容なども含めて総合的に交渉することが重要です。また、住宅ローンの条件や火災保険の内容についても、事前に相談しておくと安心です。
モデルルーム物件購入のデメリットと対策

主要なデメリット
- 選択肢の限定性: 1物件1住戸しか存在しないため、間取りや立地の選択肢が限られます。
- 使用感の存在: 多くの見学者が出入りしているため、新築とは異なる使用感があります。
- 税制優遇の制限: 中古扱いとなる場合、新築向けの税制優遇を受けられない可能性があります。
- 個性の欠如: 展示用にデザインされた空間のため、個人の好みとは異なる場合があります。
対策方法
これらのデメリットに対しては、事前の十分な調査と専門家への相談が有効です。税制については税理士、住宅ローンについてはファイナンシャルプランナー、物件の状態については住宅診断士などの専門家を活用することをお勧めします。
まとめ:賢い選択のために
モデルルーム使用後の物件は、価格面や設備面で大きな魅力があります。新築同等の住環境を、リーズナブルに手に入れたい人にとって、非常に魅力的な選択肢です。
しかし、法的には中古扱いとなるケースが多く、税制面や保証内容に関して新築と同様の恩恵を受けられない可能性があります。購入前には、しっかりと情報を収集し、状態や条件を確認することが重要です。
特に重要なのは、住宅ローン控除などの税制優遇制度の適用可否、瑕疵保険の加入可能性、設備の保証期間などです。これらの情報を正確に把握し、総合的な判断を行うことで、理想的な住まい選びが可能になります。
最終的には、個人の住まいに対するニーズと予算、そして将来的な住環境への期待を総合的に考慮し、専門家のアドバイスも参考にしながら慎重に判断することが、後悔のない住まい選びにつながります。
建物の品質、地域の将来性、住環境の利便性なども含めて、長期的な視点での検討を行うことで、モデルルーム使用後物件の購入が人生の重要な選択として成功することでしょう。